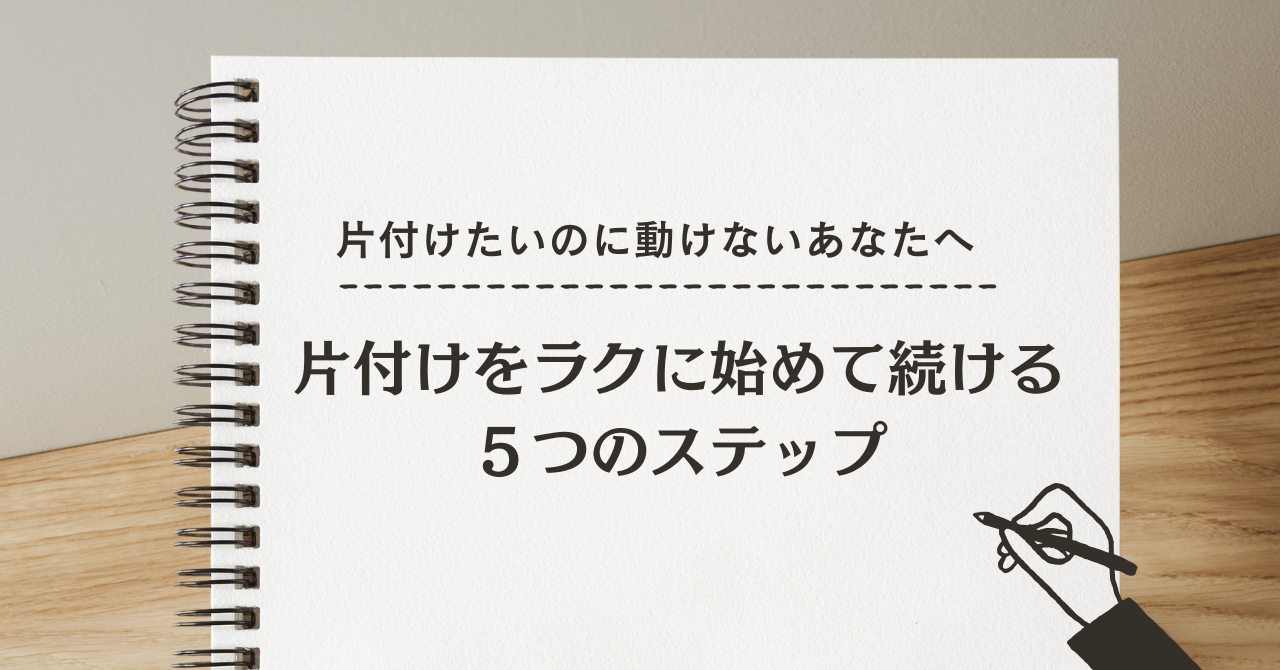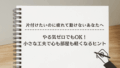「片付けたいのに、なぜか体が動かない…」そんな自分にモヤモヤしたことはありませんか?
私も昔から片付けが苦手で悩んでいました。「わかってはいるけど、やる気が出ない!」
このままではまずい!と思い、あらゆる片付け本を買い集めて片っ端から読んでみたんです。
すると、どの筆者も同じ様なことを言っていました。
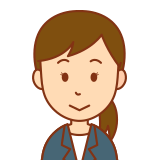
「片付けられない人は物が多すぎるから、まずは減らそう!」
でもどこから手をつければいい?
やる気をどうやって出す?
この記事では、片付けたいけど動けない人が一歩踏み出せるようになるヒントをお届けします。
こんな方必見です
・片付けが苦手な方
・忙しくて片付ける時間がない方
・片付けるやる気が出ない方
小さな工夫と考え方のコツで、今日から片付けがラクになる方法を、経験談を交えながら具体的にお伝えします。
片付けたいけど動けない3つの理由
この章では、「片付けたいけど動けない」と感じる原因を3つに分けて解説します。
自分がなぜ動けないのか理由がわかると、「やる気が出ないのは怠けているからじゃない」と安心でき、解決のための具体的な一歩が見えるようになります。
理由を理解すれば「できない自分」にイライラする代わりに、「どうすればできるか」を考えられるようになるからです。
私も以前、片付けを始めようと決意しても、「どこから手をつければいいの?」と考えているうちに夕暮れに、、結局動けなかった経験があります。
まずは自分を見つめ直してみることから始めてみましょう。片付けられない理由が分かれば、「やる気が出ない自分」へのモヤモヤが減り、片付けを始めるきっかけがつかめるはずです。
何から手を付けていいか分からない
片付ける場所が多すぎて混乱し、どんどんやる気を失ってしまいます。それは脳が混乱して判断ができなくなる状態になっているんです。
その結果、放置→さらに散らかる→またやる気がなくなる、という悪循環に。
私は家のごちゃごちゃを見ただけでやる気が失われて思考停止、行動がストップ状態になっていました。
完璧を目指し過ぎて手が止まる
「片付け=家じゅうを一気にきれいにする!」だと思っていませんか?
実はこの考えが片付けの妨げをしてしまっているんです。
「一気に完璧にやらないと意味がない」という思考で「次の連休に片付けるぞ」などと着手を先延ばしにし、結果的に散らかったままになってしまうんです。
私も、SNSで見る整った部屋に憧れ、汚部屋状態から一気に理想へ近づけようとして挫折。目標が高すぎるのも行動を止める原因でした。
片付けなくても生活できてしまう
片付いていない部屋でも平気で生活できる理由は単に「ズボラだから」や「気にならない性格だから」だけではなく、いくつかの背景があります。
片付いていないのに生活できる背景とは?
- 人間の脳は同じ景色や刺激を繰り返し見ると”慣れ”が起き、最初にあった違和感やストレスを感じにくくなる
- 「片付ける」という行為は時間・体力・判断力を消費するため、優先順位が低い人にとっては後回しになりやすい
- 子どもの頃から物が多い家や片付け文化のない環境で育つとそれが「普通」になる
私の母親も片付けが苦手で、子供の頃からいつも家の中がぐちゃぐちゃでした。それが当たり前だったので片付け方がわかりませんでした。
多くの人は、「片付けられない私はダメな人間」「三日坊主の私はダメな人間」と思ってしまう。(中略)最初はできなくてあたりまえ。
やましたひでこ著「断捨離で日々是ごきげんに生きる知恵」より引用

できないのがあたりまえ!と言ってくれて本当に救われました!
まず片付けるべきはここから!やる気を起こすスタートポイント
この章では、片付けのやる気を自然に引き出す方法とスタートポイントをご紹介します。
片付けの「やる気スイッチ」を押すコツは脳に「片付けは負担が少なく、気持ちいいこと」と覚えさせるのが重要です。
なぜなら、脳は「不快や負担を感じる行動」を本能的に避け、「達成感を感じる行動」は繰り返そうとする性質があるからです。
つまり、小さな片付けでも達成感を伴えば、脳が「またやりたい」と信号を出すようになり、自然と行動が続くようになります。
これを知ると、「始められない」を一気に突破できますよ。
片付けのやる気が出る具体的な方法とは?
片付けのやる気を出す一番の近道は、「全部やろう」とせず、小さな成功体験を積み重ねることです。
完璧な片付けを目指すと脳が負担を感じ、スタートすらできないからです。
私も「小さな成功」を意識する事でみるみる部屋が片付いていきました。
「小さな片付け」のポイント
- 視界を切り取る
机の右半分だけ、引き出し1段だけなど範囲を極端に限定します。
- 動作を1種類に固定
今日は「床の紙類を拾うだけ」や「ゴミだけ捨てる」など、判断を減らします。
- 達成感を先に作る
小さくても「やった!」と思える範囲を片付け、写真を撮ったり声に出して褒めま す。
- 着手トリガーを決める
歯磨き後やお風呂を沸かす間など、日常動作にくっつけて始めます。
たとえ5分でも、それは立派な一歩なんです。まずは「ほんの一部」だけに集中しましょう。
やがて「部屋全体を片付ける自分」に自然と変わっていきます。
まず始めに片付ける場所とは?
片付けの最初の一歩は、日常でよく目に入る場所から始めると効果が倍増します。
・いつも家族で食事をするダイニングテーブル
・玄関の靴
・キッチンの作業台
「スッキリ感」を何度も体験できるため、やる気が自然と持続します。
私の家族もスッキリしたダイニングテーブルを見て、段々と片付けに協力的になってくれました。

私は階段下の収納から始めて挫折しました。目標は小さく、目につくところからが鉄則です!
片付けは「小さく始めて成功体験を積む」+「よく目に入る場所から」が最強コンビです。
ぜひ意識しながら片付けを始めてみてください。片付けって楽しいかも!とだんだん思えてくるんです。
片付けが苦手でも続けられた!“見ないで捨てる”の使い方
片付けを途中で挫折しないためには、「見ないで捨てる」という方法が効果的です。
物を一つひとつ見て判断する作業は、想像以上に脳のエネルギーを消耗します。
だからこそ、あらかじめ「これは見ずに処分」と決めておけば、迷う時間もストレスも大幅に減らせます。
この章では、片付け初心者でも安心してできる「見ないで捨てる」方法を解説します。
時間短縮と決断力アップの両方に役立ちます。
片付けの最大の敵は?
片付けの最大の敵は「判断の多さ」です。
物を手に取るたびに「いる?」「いらない?」と考えると、脳は疲れて決断力が落ち、途中で挫折しやすくなります。
しかし、事前に捨てるルールを作ってしまえば、判断回数を限りなく少なくでき、片付けが一気に進みます。
「見ないで捨てる」具体的な方法は?
”中身を確かめてから””もう一度読んでから”と今まで「なんとなく」保管していたものを中をみないでそのまま捨ててしまいます。
中身を確かめずに捨ててしまっても良いものの例
手元に来た段階で見ないで捨てるもの
・郵便受けに入っているDMやチラシ
・強制的にもらったカタログやパンフレット(見ないと決める)
一定期間経ったらまとめて捨てるもの
・何年もしまいっぱなしの雑誌・本・資料
・年賀状(お付き合いの形としての保管期限を決めて処分)
・引っ越しの時のままの段ボール(開けずに一定期間経過=不要と判断)
辰巳渚著『新「捨てる!」技術』に掲載されている、捨てるための多彩なテクニックを活用しています。

他にも捨てる技術がたくさん掲載されていて、読むとどんどん捨てたくなります。
ポイントは、「見たら迷うものは見ない」こと。
「もしかして使えるかも…」という心理は、見てしまった瞬間に強くなります。
逆に、最初から見ずに処分すれば、感情のブレーキがかからずにスムーズに片付けられます。
捨てられないときの“減らす思考”
どうしても捨てられない物は、無理に捨てる必要はありません。
「これはまだ使えるから…」と考えてしまい、捨てられない事もありますよね。
捨てられないときに有効なのは、捨てる代わりに「減らす」意識を持つと進めやすくなります。
捨てられないけど物が多い時は「ゼロにする」という発想ではなく、「量を減らす」という柔らかいアプローチなら、心理的負担が軽くなるからです。
私も食器棚の片付けで「高かったし…」「旅行の記念だし…」と色々と理由をつけて残していました。しかし、「お気に入り以外は3個まで」とルールを決めたら、思った以上にスムーズに減らせました。
この章では、手放しやすくなる”減らす思考”の実践法をご紹介します。
捨てられないのはどうしてなのか?
「捨てられない」に隠れた心の中を理解すればあなたも自分に合った手放し方を見つけられます。自分の心と向き合うことで「どうして捨てられないのか」が明確になり、捨てる基準がハッキリしてくるからです。
あなたはどの「捨てられない」に当てはまりますか?
・過去に払ったお金や時間を回収したくて、使わない物を残してしまう。
・物が思い出や人間関係と強く結びついている。
・「いつか使うかも」という想像が捨てる判断を鈍らせる。
捨てられないときの「減らす」方法とは?
自分の「捨てられない」考え方の傾向がわかったらあとは「減らす基準」を設けてみましょう。
「半分だけ減らす」「3つに絞る」といった段階的な方法にすれば脳が受けるストレスが軽くなります。
例えば、
・洋服なら「同じカテゴリーは5枚まで」
・食器なら「お気に入り以外は3枚まで」
・本なら「1年以内に読まなかったものは半分に減らす」
・高かったものなら「3年以内に使ってないものは売る」

もらったボールペンを集めたら、一生では使い切れない量がありました(笑)
捨てるのが苦手なら、「減らす思考」でOK!
私は「新しいものを買ったら古いものは手放す」と決め、どんどん増えない様に心がけています。自分に合った対策を使えば無理なく物を減らしていけます。
片付けのモチベーションが続く!たった5分のルーティーン
長時間の片付けは気力も体力も消耗しますが、1日5分のルーティーンなら無理なく続けられます。
なぜなら、短時間なら「やらなきゃ」という重さがなく、逆に「これくらいならできそう」と思えるからです。
私は出勤前に5分だけリビングを片付ける習慣をつけた結果、今まで繰り返していたリバウンドがなくなりました。
この章では、モチベーションが下がらない”5分ルーティーン”の作り方を解説します。
片付けのモチベーションが続かないのはなぜなのか?
片付けを始めたときは「よしやるぞ!」と気合が入っていても、数日経つとやる気がしぼんでしまう…そんな経験はありませんか?
片付けを「連休のイベント」や「特別な行事」のように捉えているとすぐにリバウンドしてしまいます。片付けは毎日の生活の一部として積み重ねるもの。
習慣化の視点がないと、「やるときだけ頑張る→しばらく放置→また散らかる」という繰り返しになり、モチベーションも長続きしません。
だからこそ、最初から長時間やるのではなく、短時間・小さな範囲で成果を感じられる方法に変えることがポイントなのです。
今すぐ試そう!5分ルーティーンの方法とは?
ルーティーン化をするには「毎日やりたい」と思える事が重要です。負担があると脳は、たちまち片付けをやりたくなくなってしまうからです。
私は「出勤前に使わない物を見つけ、捨てる」「就寝前に出しっぱなしの物をしまう」と決めて大好きな曲を聞きながら毎日繰り返し行っているうちに、不思議と片付けが全く苦にならなくなってきました。
あなたも自分の生活スタイルに合ったルーティーン化できる「時間の隙間」を見つけてみてくださいね。
ルーティーン化のポイント
・ルーティーンの時間を固定する
「ご飯の後」や「就寝前」など必ず訪れるタイミング
・範囲を極小にする
「ソファの上だけ」「キッチンのシンクだけ」小さな達成感が大事
・見える場所から着手する
片付けた後のスッキリ感が大きい場所を優先的に
・完璧を目指さない
「ここだけやればOK」という気持ちで取り組むと、プレッシャーが消えます
・プラス1の楽しい習慣を入れる
最後に「気持ちが上がるアクション」を加えると片付けが楽しみになります
・アロマを1プッシュ
・キレイな状態を写真に取る
「片付け=ちょっと嬉しい時間」になると、やめたくなくなります
片付けが苦手な人に「毎日決まった時間、片づける習慣がありますか」と聞くと多くの人が「ない」。(中略)ものを定位置に戻す習慣がなく、それを修正する時間をとっていなければ、片付かないのは当然です。
西原三葉著「『片付けられない』…をあきらめない!」より引用
私もそうでした。私は「散らかったら片付ける」から「毎日片付ける」に変えたら、みるみる部屋がきれいになりました。
5分ルーティーンは小さな達成感を毎日積み重ねる方法です。毎日が積み重なりやがて大きな成果となってきます。
音楽を流すのもおすすめです。私は「今日は疲れてるし1曲分だけ」「今日は元気だから3曲分いっちゃおう!」
なんて日もあります。
たった5分であれば、片付けは苦痛ではなく”習慣”になります。
まとめ
この記事では、片付けたいけど動けないのは、決してあなたが悪いのではなく、心理的ハードルにあることをお伝えしました。そのハードルを越えるためには、まず理由を知ること、そして小さなスタートポイントを押さえることが大切です。
さらに、”見ないで捨てる”や”減らす思考”といったテクニックを取り入れれば、誰でも行動に移せるようになります。
例えば、1日5分の片付けルーティーンを続けるだけで、気づけば家全体がスッキリし、年末の大掃除がほとんどいらない生活が手に入ります。
今日からできる一歩は、小さくても十分です。ハードルを下げて、気持ちも空間も軽やかな暮らしを始めましょう。